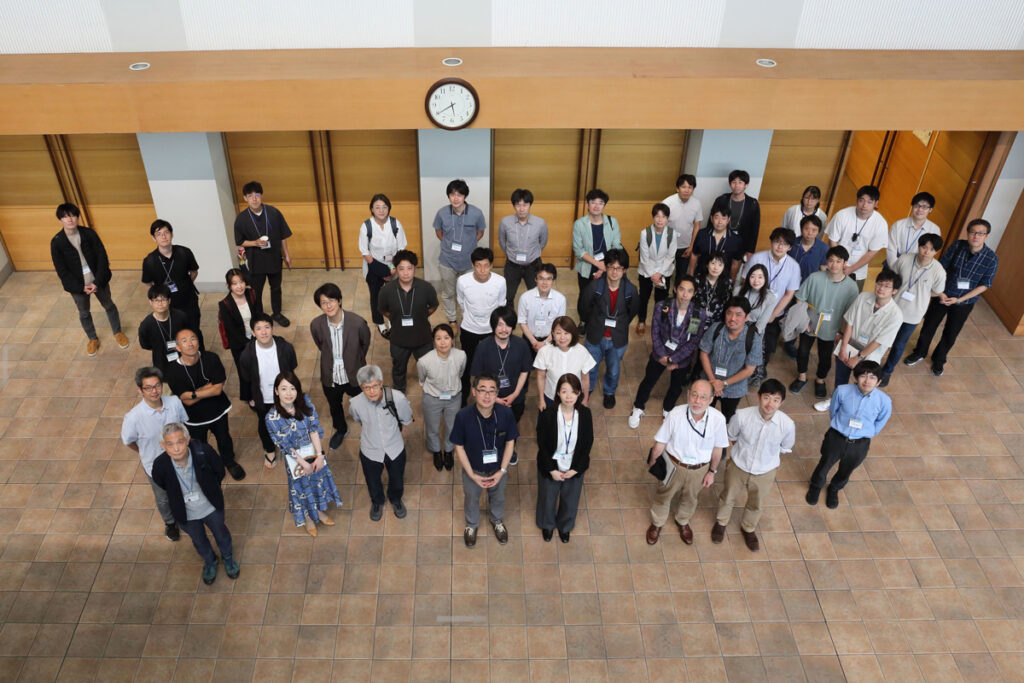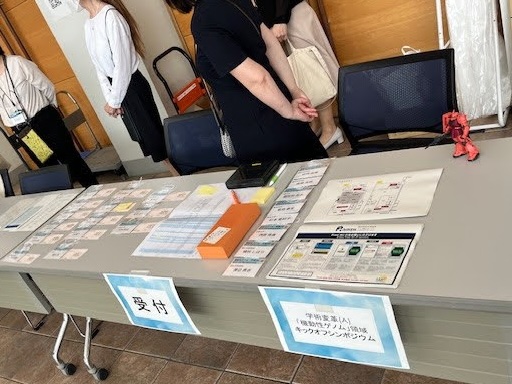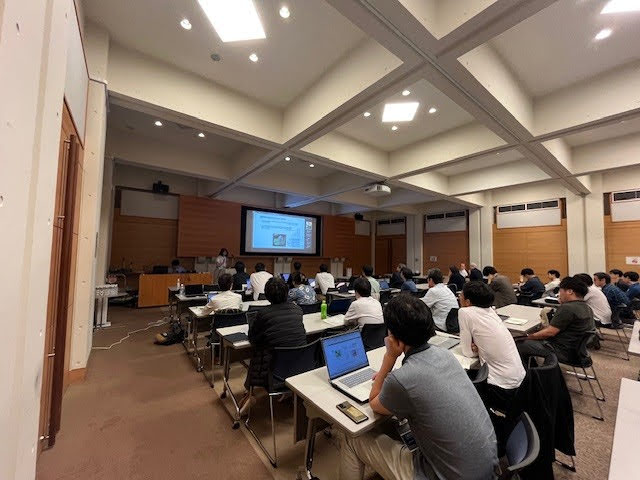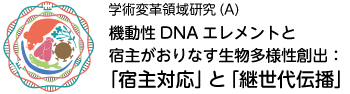「機動性ゲノム」第1回領域会議・キックオフシンポジウムが開催されました
2025年5月22日(木)理研横浜において本領域「機動性ゲノム」第1回領域会議・キックオフシンポジウムが開催されました。シンポジウムはオンサイトの一般公開とzoomオンラインのハイブリッド形式で行われ班員関係者と合わせて総勢130名ほどの参加があり盛況に終わりました。
シンポジウムの冒頭では、石黒領域代表から本領域が課題とする「機動性ゲノム」の概要について説明がありました。まず、「機動性DNAエレメント」とはものものしい造語ですが、この言葉が意図するものが何を研究対象とするものかについて解説がありました。この場では「機動性DNAエレメント」と宿主の間にある共存関係の成立過程、表現型の多様化や種分化にどのように寄与しているのかを解き明かすことが学術的問いであるということや、計画研究班の構成や領域運営の方針について領域代表の考えが示されました。過去の既存の領域と比較しても、動物・植物など多様な生物種を扱う計画研究体制が特色であることや、サステナブルな領域となるよう多くの若手研究者が参画していることや、国内の領域研究のロールモデルとなるように、女性研究者の活躍を積極的に推し進める方針が紹介された。さらに基盤技術支援を充実させて密接に連携する体制を目指すことも紹介されました。
引き続いて、計画研究の班員より研究計画の概要の説明がありました。「A01: 宿主対応」では、「機動性DNAエレメント」と「宿主ゲノム」との相互作用で 新たに生じたgenetic/epigeneticな変化、あるいはTADなどのクロマチン高次構造が、宿主にどのように影響しているのか、また宿主がどのように対応して、新規共存を築いているのかをテーマとしていること、「A02: 継世代伝播」では、新規のゲノム機能が生殖系列を通じてどのように固定され、表現型多様化への寄与するのか、というテーマに取り組むことが説明された。各計画研究が目指す具体的な方向性や領域内の相互連携の礎となる技術について発表が行われて、班員の相互理解が深まるシンポジウムであると共に、一般参加者をはじめ公募班への応募を検討する研究者に向けての強力なアピールの場ともなったと思います。さらに懇親会の場においても引き続いて活発な意見交換が行われました。
本会議には、総括班評価委員として佐々木裕之先生(九大)、角谷徹仁先生(東大)、石野(金児)知子先生(東海大)、学術調査官の村木則文先生に参加を頂き意見交換やご意見伺いました。
またキックオフシンポジウムに先だって総括班会議も行われました。本領域の概要と運営体制について領域代表から説明があったのち、 国際活動支援、先端技術の共有、共同研究の推進、HPを通しての成果発信などの広報活動、今後の活動スケジュールなど、総括班の活動方針について意見が共有されました。
最後に、この「機動性ゲノム」第1回領域会議・キックオフシンポジウムに参加して最も感動したのは、受付のコーヒーの所にガンプラを飾ってくれていたことです。理研の運営の皆さんの中に誰か、ワシときっと理解かりあえるニュータイプがいると思いました。理研の運営の皆さんの心意気ありがたく頂戴して、この5年間領域活動を盛り上げていけるよう尽力していく決意をあらためて感じる会となりました。どうぞよろしくお願いいたします。
領域代表 石黒